入院している大切な人に「お見舞いのお花」を贈りたいと考えたとき、単に見た目の華やかさだけで選んでしまっていませんか?
実は、お見舞いにふさわしくないNGな花や、マナー違反になる贈り方もあり、知らずに渡すと逆効果になってしまうこともありますよ。参考にされてくださいね!
この記事を読むとわかること
- お見舞いにふさわしい花の選び方とおすすめの種類
- 避けるべきNGな花・マナー違反の具体例と理由
- 訪問や贈るタイミング・熨斗や快気祝いのマナー
お見舞いにふさわしい花は?迷ったらアレンジメントがおすすめ

お見舞いの場面で花を贈るとき、第一に考えるべきは患者さんの体調や病室の環境への配慮です。
ただ見た目が綺麗なだけでなく、扱いやすさや飾りやすさも重要なポイントになります。
そんなときに最も無難で喜ばれやすい選択肢が「フラワーアレンジメント」です。
花束よりも花籠やアレンジメントが喜ばれる理由
花束は花瓶が必要ですが、入院中の病室には花瓶が用意されていないことも多く、かえって負担をかけてしまうことがあります。
その点、花籠にアレンジされたフラワーギフトなら、置くだけで飾れる手軽さが魅力です。
水替えの手間も少なく、病室での管理もしやすいため、患者さんや看護スタッフにとっても安心です。
おすすめの花:ガーベラやパステルカラーのアレンジが無難
お見舞いに贈る花として特に人気なのが「ガーベラ」です。
ピンクのガーベラは「崇高な美しさ」、オレンジは「我慢強さ」、黄色は「究極の美しさ」と、前向きで希望を与える花言葉を持っています。
また、パステルカラーのアレンジメントは、誰からも好まれやすく、病室の雰囲気を明るくする効果もあります。
このように、花選びは「患者の負担にならない」「花の意味が前向き」「見た目も明るく華やか」というポイントを意識すると、自然と喜ばれる花になります。
迷ったときは、シンプルで明るい色合いのフラワーアレンジを選びましょう。
絶対に避けるべきお見舞いの花とタブー
お見舞いの花には、見た目の華やかさだけではなく「縁起」や「病院の環境」への配慮も欠かせません。
知らずに贈ると失礼になってしまう花や、患者さんに不快感を与えるような花も存在します。
ここでは、絶対に避けたいお見舞いの花のNG例とその理由を具体的に紹介します。
鉢植えは「寝付く」ことを連想させNG

鉢植えの花は「根がつく=寝付く」とされ、病気が長引くことを連想させるため、お見舞いの贈り物としては避けるのが一般的です。
特に年配の方には縁起を気にする人も多く、マナー違反と受け取られる可能性があります。
ただし、命に関わる病気でない場合や、長期入院のケースでは例外的に喜ばれることもありますが、慎重に判断すべきでしょう。基本的におすすめはお店ではしていません!
香りが強すぎる花・散りやすい花・花粉が多い花は避けよう
強い香りのある花は、病気で嗅覚が敏感になっている患者さんにとって負担になることがあります。
また、花粉が多い花や散りやすい花は、病室の掃除が大変になったり、アレルギーや感染症の原因にもなるため、避けましょう。
特に避けたいのは、ユリ(香りが強く花粉も多い)、カスミソウ(散りやすい)、スギ・ヒノキ(アレルギーの原因)などです。
色や本数にも注意!「白・赤」や「4本・9本」は不吉とされる

白い花は法事を連想させるため、特に白一色のお花は避けましょう。
また、赤い花は「血」や「火」を連想させるため、お見舞いにはふさわしくないとされています。
花の本数についても注意が必要で、「4本(死)」「9本(苦)」という数字は不吉とされ、避けるのがマナーです。
避けたい具体例:シクラメン・キク・ツバキなど
シクラメンは「死」「苦」を連想させる名前で、代表的なNG花のひとつです。
キクの花は葬儀や仏花のイメージが強く、ツバキは「花が首ごと落ちる」という理由から縁起が悪いとされています。
これらの花はたとえ美しくても、お見舞いの場には不向きですので、他の前向きな意味を持つ花を選ぶようにしましょう。

病院への持ち込みマナーと確認ポイント
お見舞いの花を贈る前に、必ず確認すべきことがあります。
それは「病院のルール」や「病室の環境」です。
せっかくの心遣いが、病院側の事情により受け取ってもらえないということもあるため、事前確認は非常に重要です。
お見舞いに行く前に必ず確認すべきこと
お花の持ち込みが可能かどうかは、病院や病棟によって異なります。
最近では、感染症予防やアレルギー対策として生花の持ち込みを禁止している病院も増えています。
持ち込み可能かどうかは、必ず事前に病院、またはご家族に確認してからにしましょう。
病院によっては花の持ち込みが禁止されている場合も
特に集中治療室(ICU)や免疫力の低い患者が多い病棟では、花に含まれる菌や花粉がリスクになるため、厳しく制限されていることがあります。
また、ドライフラワーやプリザーブドフラワーでさえ禁止されている場合もあるため、注意が必要です。
一見きれいに見える花でも、患者さんにとっては負担やリスクとなることがあるため、自己判断せず確認をするのがマナーです。
花瓶の有無や置き場所への配慮も忘れずに
花瓶がない病室では、花束をもらっても飾る場所や容器がなく困るという声が多くあります。
そのため、花瓶が不要なフラワーアレンジメントや、小さめのかご花などが実用的です。
また、相部屋では他の患者さんへの配慮も必要です。
大きすぎる花や香りの強い花は避け、邪魔にならないサイズのものを選ぶようにしましょう。
お見舞いのタイミングと訪問マナー
お見舞いの花を贈るタイミングや、実際に訪問する際のマナーも非常に重要です。
配慮に欠けた訪問は、患者さんやご家族にとって大きなストレスになることもあります。
ここでは、訪問する時期とマナーについて、押さえておくべき基本ポイントを紹介します。
入院直後や手術前後は避けるのが基本
入院して間もない時期や、手術の前後は患者本人もご家族も心身ともに非常に不安定な状態にあります。
こうした時期に訪問することは、かえって迷惑になる場合があるため、避けるのがマナーです。
訪問前には、家族や病院に状況を確認してからにするのが安心です。
ベストタイミングは回復に向かい始めた頃
お見舞いに適したタイミングは、病状が落ち着き、回復に向かっている段階です。
この時期であれば、患者本人も気持ちに余裕ができており、お見舞いの花を心から喜んでもらえる可能性が高いです。
逆に、病状が重かったり、面会謝絶の場合は絶対に無理をしないことが大切です。
長居や大人数での訪問は迷惑になることも
病室は静養の場であり、患者にとっては貴重な回復時間です。
訪問はなるべく短時間にとどめ、10〜15分程度が目安とされています。
また、複数人で押しかけたり、小さな子どもを連れての訪問は避けるのが常識です。
同室の他の患者さんへの配慮も忘れずに、静かで落ち着いた訪問を心がけましょう。
相場や熨斗(のし)のマナーも押さえておこう
お見舞いの花を贈るときは、マナーとして金額の相場や熨斗の書き方も大切なポイントになります。
形式を正しく整えることで、相手に誠意が伝わり、安心感を与えることができます。
ここでは、お花の予算からのし紙・水引のマナーまで、失礼のない贈り方を解説します。
花の予算は4,000円〜5,000円が目安
お見舞いに贈るお花の予算は、一般的に4,000〜5,000円程度が相場とされています。
これより安すぎると見た目が寂しくなり、逆に高すぎると相手に気を遣わせてしまうことがあります。
コンパクトなアレンジメントでも、色合いや花材次第で十分華やかに仕上がるため、バランスのよい贈り方を意識しましょう。
のしは「御見舞」「祈御全快」など、白赤の結び切りを
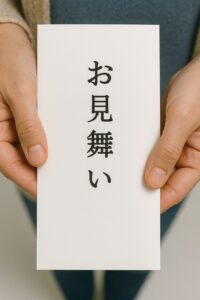
お見舞い用の熨斗紙には、「御見舞」や「祈御全快」などの表書きを使います。
水引は「白赤の結び切り」が基本で、病気が「これきりで終わりますように」という意味が込められています。
なお、「のし」そのものをつけるかどうかは病院や個人の考え方にもよるため、不安な場合は白い封筒やカードで代用するのも良いでしょう。
現金を贈る場合の封筒やマナーについて
お見舞いには現金を包む場合もありますが、市販の「御見舞」用封筒や白無地封筒に入れるのが一般的です。
表書きは「御見舞」または「祈御全快」とし、下段に自分の名前を書くようにします。
会社名義で贈る場合は、右側に会社名、左側に代表者名を記載するのが慣例です。
間違っても不祝儀袋を使うことのないよう、注意が必要です。
快気祝いのお返しにも注意が必要
お見舞いをいただいたら、退院後には「快気祝い」という形でお返しをするのが一般的なマナーです。
どのタイミングで何を贈るべきか迷う方も多いため、ここでは快気祝いに関する基本的なルールをわかりやすく解説します。
感謝の気持ちをきちんと伝えるためにも、正しいマナーを知っておきましょう。
快気祝いの時期は退院後10日以内が目安
快気祝いを贈るタイミングは、退院・床上げ・仕事復帰などの節目から10日以内が基本とされています。
「きれいに治った」という節目があれば、早めに感謝の気持ちを形にするのが望ましいです。
療養が長引いたり、完治しきっていない場合には「御見舞御礼」や「快気内祝」という表書きで対応します。
お返しは「後に残らない消え物」が一般的
快気祝いの品物には、石鹸、タオル、砂糖、お菓子などの「消え物」が定番とされています。
これは、病気が残らず消え去った=快復したという意味を込めているためです。
高額なものを選ぶ必要はありませんが、相手の好みや家族構成などを考慮して選ぶと、より喜ばれます。
表書きの書き方やのしの種類も要チェック
快気祝いの熨斗(のし)は、「快気祝」または「快気内祝」という表書きを使いましょう。
水引は白赤の「結び切り」が基本で、回復が「一度きり」であることを表します。
贈り主の名前は下段に記載し、家族や会社名義で贈る場合は表記に注意してください。
形式ばかりにとらわれる必要はありませんが、基本のマナーを押さえることで、相手にしっかりと感謝が伝わります。
お見舞いの花選びとマナーに迷ったときのまとめ
お見舞いの花を贈るときは、見た目の美しさだけでなく、マナーや患者さんへの配慮が何よりも大切です。
適切なタイミング・品物・言葉・相場を理解することが、真心のこもったお見舞いになります。
ここでは、記事全体を通して押さえておきたいポイントを簡単に振り返ります。
- 鉢植えや香りの強い花はNG、アレンジメントが無難
- 白・赤・不吉な本数(4本・9本)は避ける
- 訪問は病状が安定してから、短時間・少人数で
- 熨斗は「御見舞」「祈御全快」、水引は白赤の結び切り
- 快気祝いは10日以内、「消え物」で感謝を伝える
相手の立場に立った思いやりが何よりも重要です。
迷ったときは、病院やご家族に相談しながら、失礼のない形で気持ちを届ける方法を選びましょう。
心からの「お大事に」の気持ちが伝わるお見舞いこそ、患者さんにとって最高の励ましになります。
この記事のまとめ
- お見舞いにはアレンジメントフラワーが最適
- 鉢植えや香りの強い花はNGとされる
- 「白・赤」や「4・9本」は縁起が悪く避けるべき
- 病院によっては花の持ち込み自体が禁止されている
- 訪問のタイミングは回復期がベスト
- 相部屋ではサイズや香りに特に配慮が必要
- のしは「御見舞」や「祈御全快」、白赤結び切りを使用
- 快気祝いは10日以内に「消え物」で感謝を伝える



コメント